※本記事は、過去に書いた内容です。
現在のCampus Labでは、助言や情報提供ではなく、学びや考察の記録を目的としています。
シリーズ:手数料に惑わされない投資判断 ― 安さの裏にある構造と、見逃しがちな価値(第1回)
「手数料を払いたくない」「銀行やIFAよりネット証券の方が得」――そう思ったことはありませんか?
確かに、手数料は投資成果を左右する大事な要素です。
しかし、それだけを基準に判断してしまうと、本来得られるはずの“価値”を見逃してしまうこともあります。
手数料は「手間賃」や「サービスの対価」
投資信託の手数料(信託報酬など)は、単なるコストではなく「代行の費用」です。
運用会社や販売会社が投資先を選び、情報を分析し、リバランスや報告を行う。
この「時間と知識」を代わりに担ってもらう対価が手数料です。
自分で市場分析・運用判断を行うなら低コスト商品で十分。
しかし、専門家の知見やサポートを受けたい場合は、手数料という“時間の代金”を払うことも合理的です。
「手数料=損」と感じる理由
日本では、長期にわたる低金利と「倹約は美徳」という文化の中で、「ムダな支出を避ける」感覚が強く根づいています。
その結果、「確実に引かれる手数料」は“損”に感じられやすいのです。
しかし本来、手数料の高低は損得ではなく、「自分がどこまで手間を担うか」の違いにすぎません。
手数料とリターンの関係
2025年10月14日更新の日経電子版によると、
投資信託の純資産総額ランキング上位は以下の通りです(出典:日経電子版 https://www.nikkei.com/)。
- 1位:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- 2位:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- 3位:A・バーンスタイン・米国成長株投信D
上位2位はどちらも信託報酬が極めて低く、インデックス型の代表格です。
一方で、同ランキング8位の
netWIN GSテクノロジー株式ファンド(B・ヘッジなし)は、信託報酬が約2%と高いものの、
直近3年の年率リターンは35.17%とS&P500の24.45%を上回っています。
(出典:楽天投信スーパーサーチ https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/search/)
つまり、高い手数料が必ずしも悪いとは限らないということです。
※特定の商品を推奨する意図はありません。
まとめ
手数料は“悪”ではなく、“選択の代償”です。
必要以上に高ければ避けるべきですが、必要なサポートに対して支払うものなら、それは合理的な支出。
大切なのは「安さ」ではなく「納得感」。
自分に合った手間とコストのバランスを見極めることが、本当の意味での“賢い選択”です。
次回は「インデックス」と「アクティブ」の構造を比較し、
手数料の違いがどこから生まれるのかを解説します。
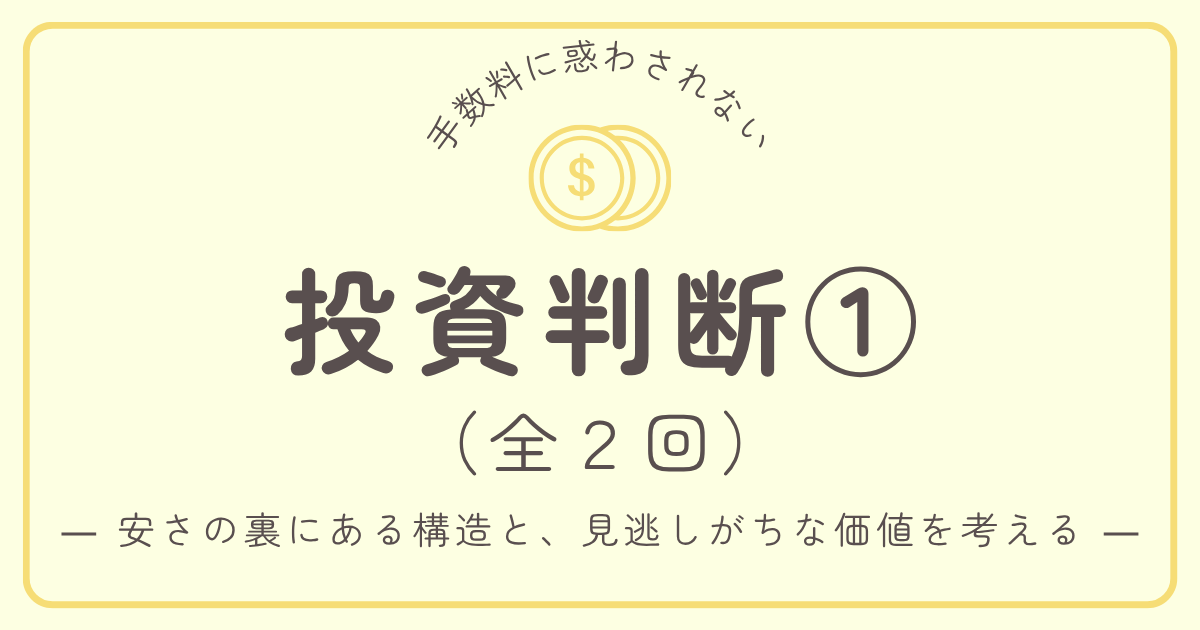

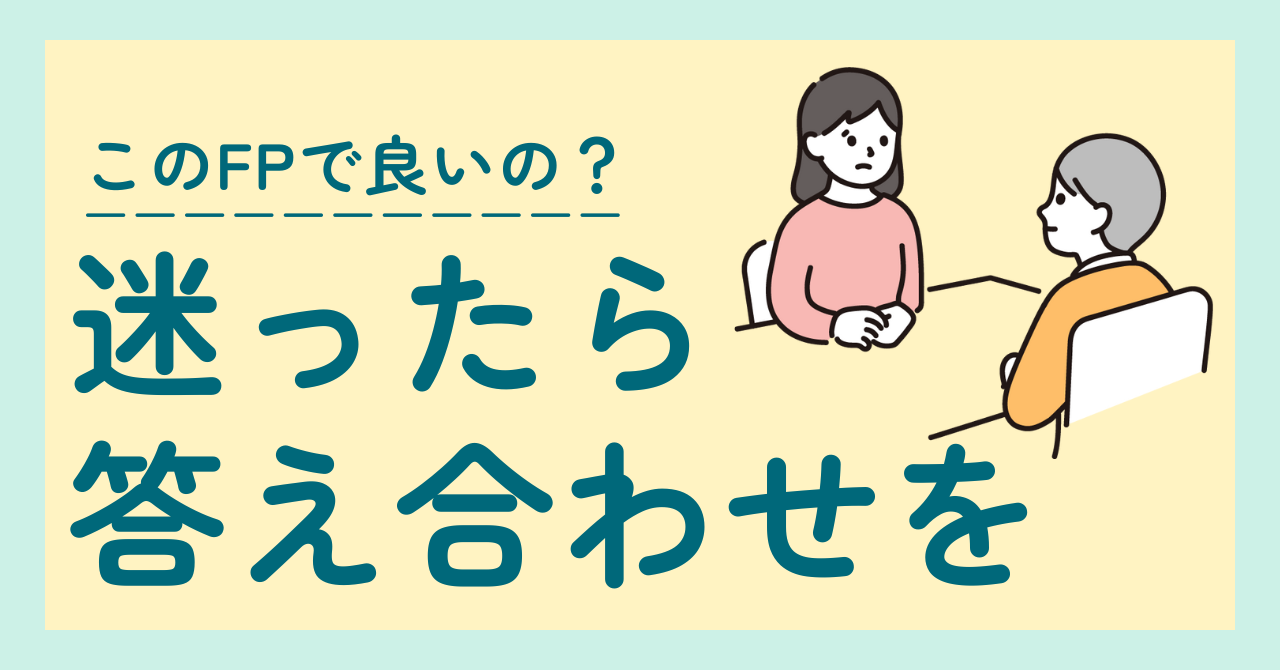
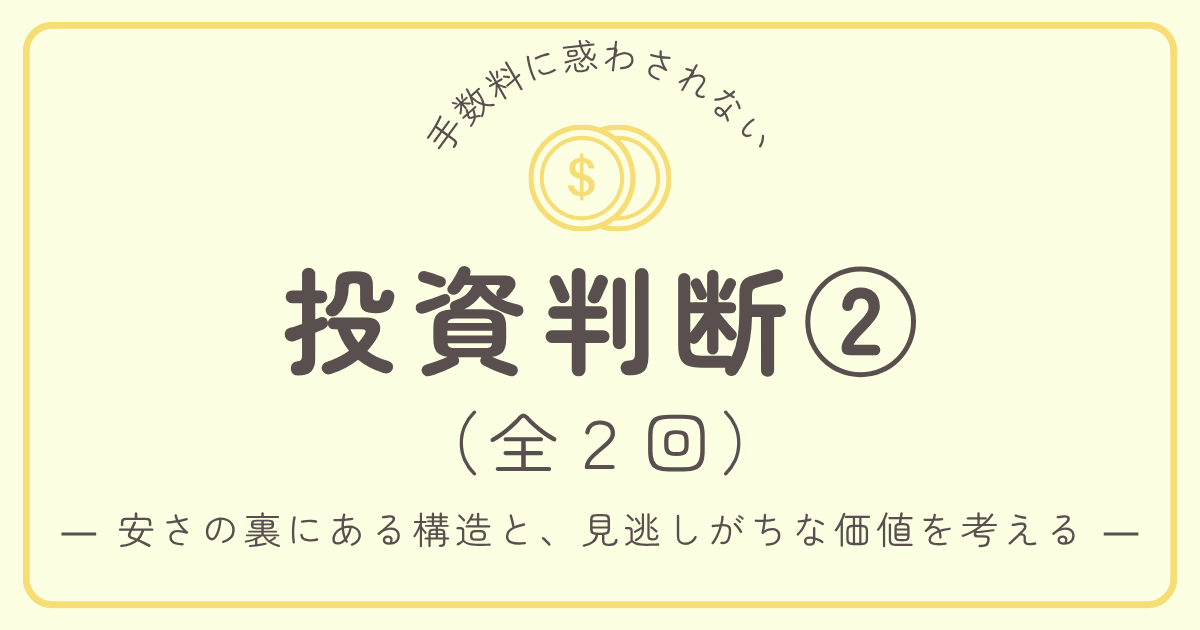
コメント