※本記事は、過去に書いた内容です。
現在のCampus Labでは、助言や情報提供ではなく、学びや考察の記録を目的としています。
シリーズ:手数料に惑わされない投資判断(第2回)
投資信託には「インデックスファンド」と「アクティブファンド」があります。
どちらを選ぶかで、手数料も、リターンも、投資スタイルも大きく変わります。
インデックスファンドとは
インデックスファンドは、株価指数(インデックス)に連動するように設計されています。
構成銘柄が自動的に決まるため、運用コストが低く、信託報酬が安いのが特徴です。
代表例はeMAXIS Slimシリーズの
「米国株式(S&P500)(信託報酬0.0814%)」と「全世界株式(オールカントリー)(信託報酬0.05775%)」。
アクティブファンドとは
アクティブファンドは、運用会社が企業を調査し、将来性を見極めて投資するタイプ。
企業訪問や分析コストがかかるため、信託報酬は高めです。
ただし、優れた銘柄選定により市場平均を上回る成果を出すケースもあります。
例:netWIN GSテクノロジー株式ファンド(B・ヘッジなし)(信託報酬2.09%)
直近3年の年率リターンは35.17%
eMAXIS Slim 米国株S&P500は24.45%
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)は21.91%
※出典:楽天投信スーパーサーチ https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/search/(10月15日現在)
市場構造とアメリカ偏重
2025年6月末時点の世界企業時価総額ランキングでは、
トップ15社中13社がアメリカ企業です(出典:みずほ銀行 https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/account/tips/topic_99.html)。
そのため、オールカントリー(全世界株式)は時価総額加重平均と言って、構成銘柄の時価総額の比率に基づいて組み込まれます。米国の時価総額が世界で大きいため、米国比率は直近でも6割超です。
S&P500も同様の加重方式で米国大型株を対象としているため、基準価額(運用実績)の動きが近くなりやすい傾向があります。
ただし、オールカントリーは非米国株や為替の影響も受けるため、完全に一致するわけではありません。
テクノロジー集中とリターンの関係
ランキング上位の銘柄をさらに見ていくと、テクノロジー関連企業が多数を占めていることがわかります。
半導体、AI、クラウドなどの分野が世界的に急成長しており、投資家の注目が集まっているためです。
特に近年では、ChatGPTを開発するOpenAIとの提携が報じられると、
その企業への期待感から株価が大きく上昇するケースも見られます。
こうした流れから、銘柄を絞り込むほど短期的にはリターンが高くなりやすい傾向があります。
テクノロジー関連株は一般的に「グロース株(成長株)」と呼ばれ、
将来の利益成長が大きく期待される一方で、金利動向に敏感です。
金利が下がると、将来の利益がより高く評価され、株価が上がりやすくなります。
反対に、金利が上昇すると割引率が高まり、将来の利益の現在価値が下がるため、
株価が下がりやすい傾向があります。
つまり、金利低下局面ではグロース株が優勢になりやすく、
金利上昇局面では一時的に調整(下落)することが多いのです。
また、地政学リスクや雇用の悪化などの外部要因にも反応しやすく、
値動きの振れ幅(ボラティリティ)が大きい点はリスクとして理解しておく必要があります。
ただし、ドルコスト平均法(定額積立)の観点から見ると、
価格変動の大きい商品は下落時に多く、上昇時に少なく購入する効果が働き、
平均取得単価を下げやすい側面もあります。
そのため、こうした商品の特性を理解しながら長期で積み立てることで、
変動を味方にできる可能性もあるのです。
まとめ
インデックスは「低コストで分散したい人」向け、
アクティブは「リサーチや銘柄集中に価値を感じる人」向け。
どちらが正しいではなく、目的とスタイルに合った選択が大切です。
集中投資はハイリスク・ハイリターン。 分散投資は安定性重視。
どちらも「正しい」投資方法であり、
自分がどのリスクを引き受けるかを理解することが、長期投資の納得感につながります。
(※特定商品を推奨するものではありません)
次回は補足コラムとして、
「なぜ日本では“安さ”や“献身”が称賛されるのか」という文化的な背景を取り上げます。
投資判断の裏側にある心理と社会の価値観を、少し柔らかく考察します。
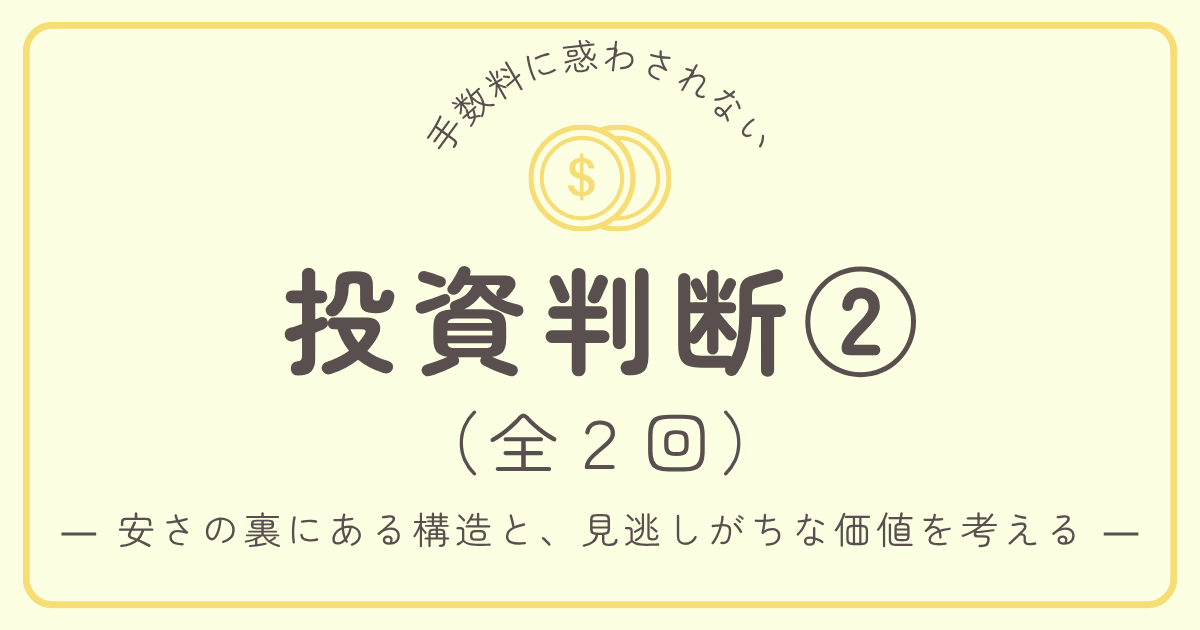

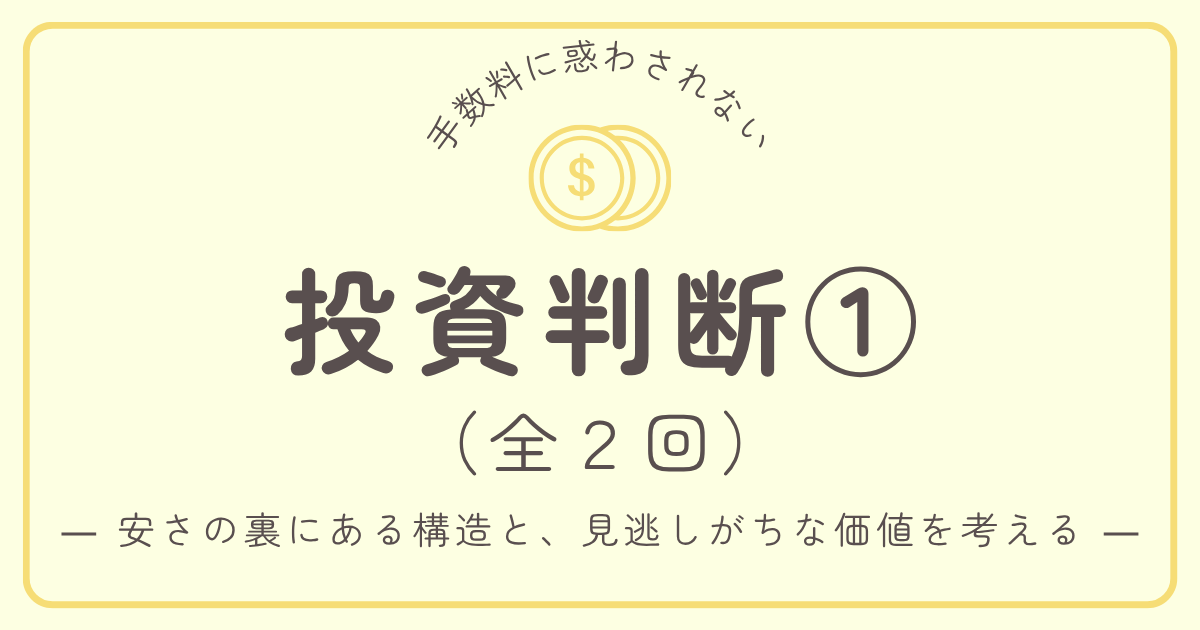
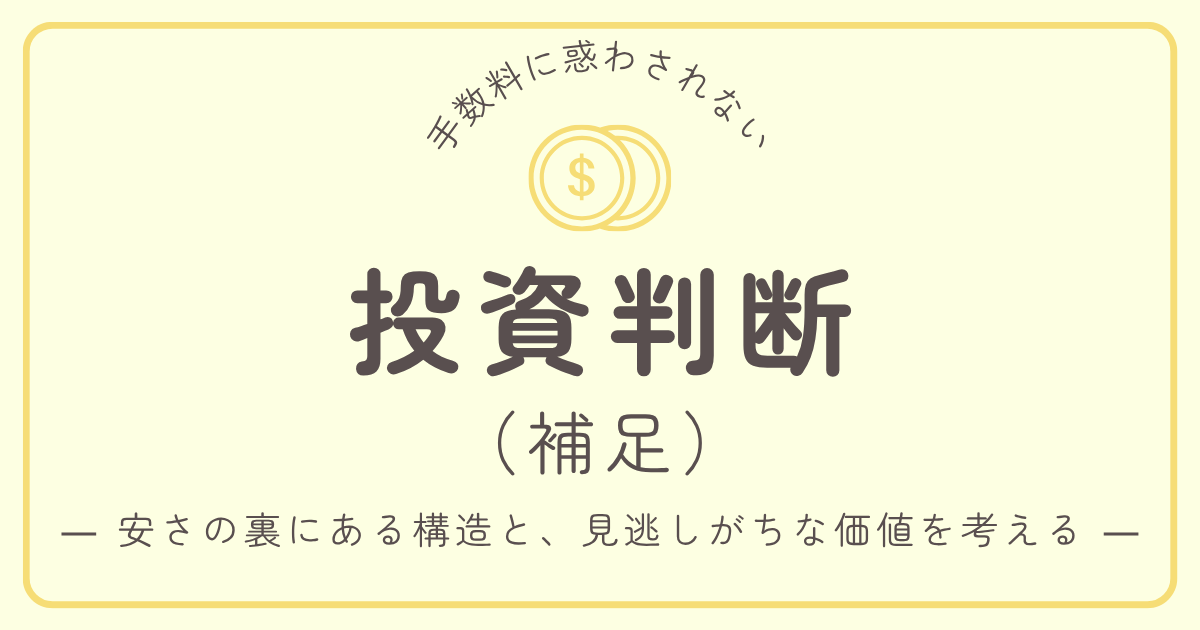
コメント