※本記事は、過去に書いた内容です。
現在のCampus Labでは、助言や情報提供ではなく、学びや考察の記録を目的としています。
「アメリカは豊かだ」と直感的に思う方は多いでしょう。確かに平均所得、生活水準、世界経済における影響力で突出しています。S&P500のインデックスファンドが日本で人気なのは、そういった考えの方が多いという表れかもしれません。
だけど、「誰にとって」「持続的に」豊かと言えるのか?
以下の観点から、アメリカの「豊かさ」を多面的に検証し、今後の長期投資の参考になれば幸いです。
- 1人当たりGDP
- 1人当たり可処分所得
- 実質賃金・平均時給の上昇+所得格差
- 物価上昇が家計に与える影響
- 財政赤字・債務の拡大と豊かさの関係
その上で「アメリカは豊かな国か?」という問いに対して、より深く考察します。
1. 1人当たりGDP
2024年、アメリカの名目1人当たりGDPは約 8.58 万ドルと、先進国の中でも高水準です。 世界銀行
この水準だけをもって「豊か」と言うのは妥当ですが、前述のように分配・物価・持続可能性の観点も併せて見る必要があります。
2. 1人当たり可処分所得(手取り所得)
最新のデータでは、アメリカの「1人当たり可処分個人所得」は 2024年に約 6.44万 ドルとなっています。 FRED
また、物価調整後(実質ベース)では、2025年8月時点で約 5.28万 ドル(2017年基準ドル)とのデータもあります。 FRED
このことから、税・社会保険料控除後に手元に残る所得水準も依然として高く、「平均所得」という観点ではアメリカは豊かであると言えます。
3. 平均時給・賃金上昇と所得格差
賃金上昇の状況として、直近のデータでは実質平均時給(物価調整後)は、2024年8月→2025年8月で +0.7 % の増加でした。 アメリカ合衆国労働統計局
平均時給そのもの(名目)は、2025年8月で約 36.53 ドル/時となっています。 FRED
つまり、賃金は上昇しているものの、物価上昇を十分上回るほどではなく、実質成長としては緩やかです。
次に所得格差です。アメリカのジニ係数(世帯・個人所得格差を表す指標)は、世界銀行のデータで約 41.8(2023年)となっており、先進国では高位にあります。 世界銀行
また、過去数十年では格差拡大が確認されており、上位1%の所得・資産集中が大きなテーマです。
したがって「平均水準は高いが、格差が大きい」という構図が鮮明で、豊かさが国民全体に均等に広がっているとは言い難い面があります。
4. 物価上昇と「困っている人」の実態
インフレ(物価上昇)の影響で、手取り・生活実感に圧力がかかっています。実質賃金の上昇が+0.7%だったというのは、物価上昇に近いかそれを下回る可能性もある水準です。
生活実感を示す調査では、例えば Federal Reserve Board の年次「Economic Well-Being of U.S. Households 2024」によると、
・「とても順調/順調」 73%、
・「なんとかやっている」 19%、
・「やっていくのが難しい」 8%
という結果でした。 Le Monde.fr
つまり、人口の 約8%程度が「やっていくのが難しい」 と感じており、これがインフレ・物価高の影響を受けていると考えられます。
5. 財政赤字・債務の拡大と豊かさの持続性
アメリカの財政状況を見てみると、2025会計年度の8月までの財政赤字総額は1兆9730億ドルに膨らんでいます。 Bloomberg
また、国債等を含む公的債務のGDP比は、2024会計年度末時点で約98%に達しており、将来はさらに拡大する可能性の高い傾向があります。 世界経済のネタ帳
このような「高債務・高赤字」の構図は、将来の利払いコスト増、税負担の上昇、成長余力の低下といった豊かさの持続可能性にとって明確なリスク要因です。
つまり、今の所得水準・生活水準が維持できるか、社会保障・公共サービスが将来も同等に提供できるか、という点で不透明性が高まっています。
結論:アメリカは豊かな国か?
結論から言うと、
「平均値で見ればアメリカは依然として豊かな国である」 というのが現状の評価です。
ただし、次の2つの大きな但し書きが付きます。
- 分配の不平等:平均1人当たり所得は高いものの、格差が大きく、全員がその恩恵を受けているわけではない。
- 持続可能性への懸念:財政赤字・債務の拡大、賃金の実質上昇の緩やかさ、物価上昇の影響などが将来の豊かさを脅かしかねない。
ゆえに、「豊かだが安心できない」「豊かさが全員に行きわたっているわけではない」という二面性を持つ国というのが、アメリカの現状を的確に表しています。
米国は「大きな富を生む場」である一方で、「格差・リスクへの備え」がこれまで以上に重要になっていると言えます。
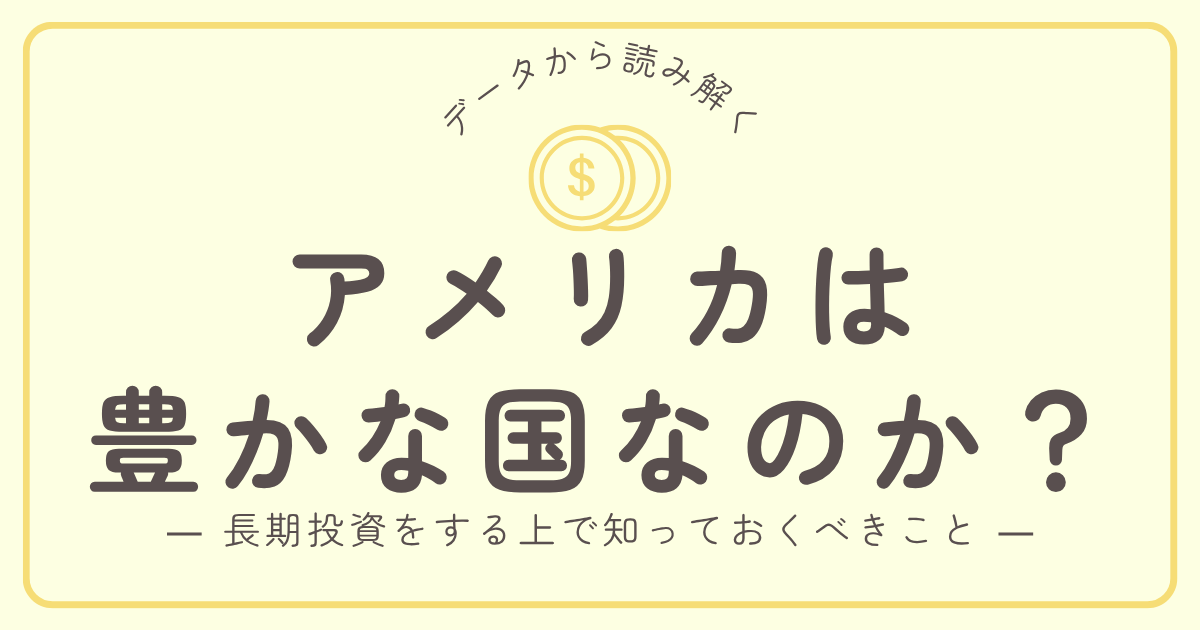

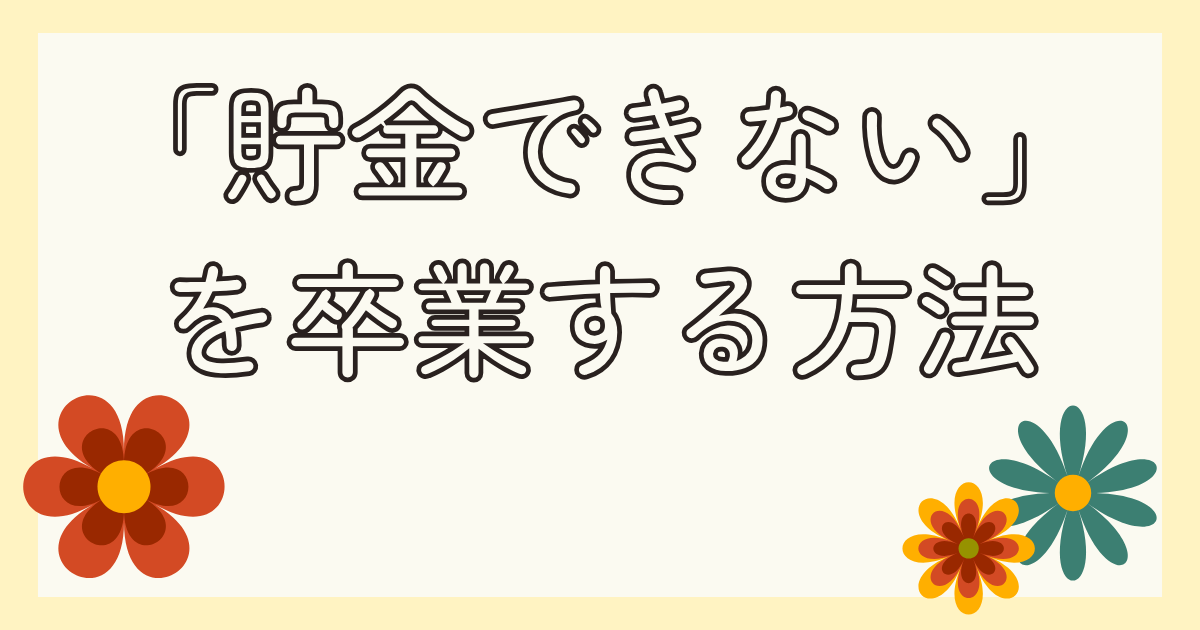
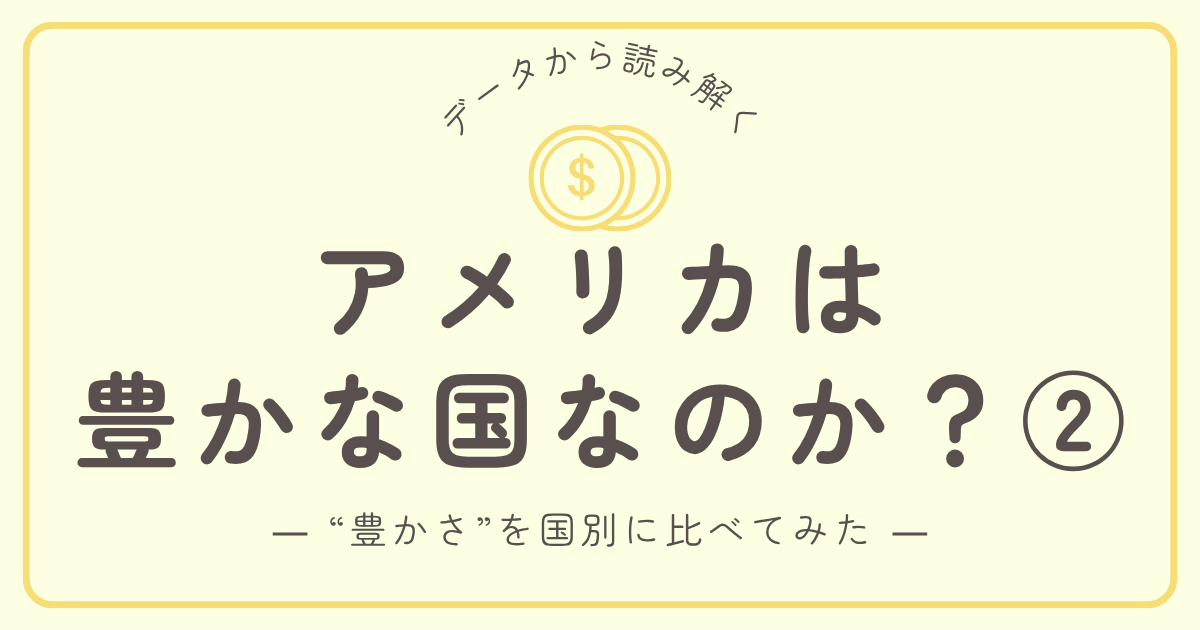
コメント