※本記事は、過去に書いた内容です。
現在のCampus Labでは、助言や情報提供ではなく、学びや考察の記録を目的としています。
大学が教育・研究を継続するうえで、寄付と基金(エンドウメント)は重要な財源です。
しかし、日米ではその規模・仕組み・学生への還元度に大きな差があります。ここでは、ハーバード大学・スタンフォード大学と、東京大学・慶應義塾大学を例に、その違いを整理します。
圧倒的な基金規模の差
アメリカでは、大学基金が桁違いの規模にあります。
ハーバード大学は約5兆円超、スタンフォード大学も約4兆円規模。
一方、日本は、東京大学で約600億円、慶應義塾大学は数百億円規模。
つまり、1〜2桁の差があり、運用益に期待できる額そのものが異なります。
奨学金の厚みが違う
この差は、学生支援に直結します。
ハーバード大学は、世帯年収10万ドル(約1,400万円)以下なら、授業料だけでなく住居費・食費・保険・渡航費まで実質無償。
20万ドル以下でも授業料は不要。
さらに、学生の約55%がニーズベース奨学金を受給し、多くが無借金で卒業できます。
背景には、基金を運用し、毎年一定割合(約4〜5%)を取り崩して奨学金・研究費に充てる仕組みがあります。元本を守りつつ継続的に利益を生むため、学生支援を「恒常的な制度」として維持できます。
一方、日本はどうでしょうか。
東京大学にも授業料免除や給付型奨学金はありますが、予算制約が大きく、申請しても不承認となる可能性が明記されています。
慶應義塾大学も奨学金制度は多いものの、返済不要の給付型は限られ、平等に無償化される仕組みとは言えません。
つまり、ハーバードのように“収入に応じてほぼ無償”が幅広く実現できている大学は、日本にはまだないのが現状です。
運用という仕組みの違い
アメリカでは
寄付 → 元本として長期運用 → 毎年一部を取り崩し → 教育・研究に再投資
という循環が確立しています。
日本は、寄付金が使い切り型となることが多く、運用益を安定財源とする仕組みは限定的。
そのため、景気や予算に左右されやすく、長期視点の教育投資が難しい面があります。
日本の新しい挑戦:10兆円大学ファンド
日本でも、研究力強化に向けて**10兆円大学ファンド(JST運用)**が始まっています。
国が原資を用意し、その運用益を大学に配分する仕組みで、いわば“日本版エンドウメント”。
しかし
- 対象校は限られる
- 政策変更の影響を受けやすい
という課題があります。
アメリカは寄付が原資で、大学が自律的に運用できる点が大きく異なります。
国だけでは限界。寄付と運用への理解が未来をつくる
国の施策も重要ですが、税制や政策に依存しすぎると、将来の制度変更で不安定になる可能性があります。
だからこそ、大学自身が寄付を集め、運用して学生や研究に再投資する“自律的な循環”が必要です。
そのためには、
- 大学:透明な運用・成果の見える化
- 社会:寄付・運用への理解
が欠かせません。
少額寄付でも、多くの人が関わることで、学生の選択肢が広がり、研究が前に進む未来が実現するのだと思います。
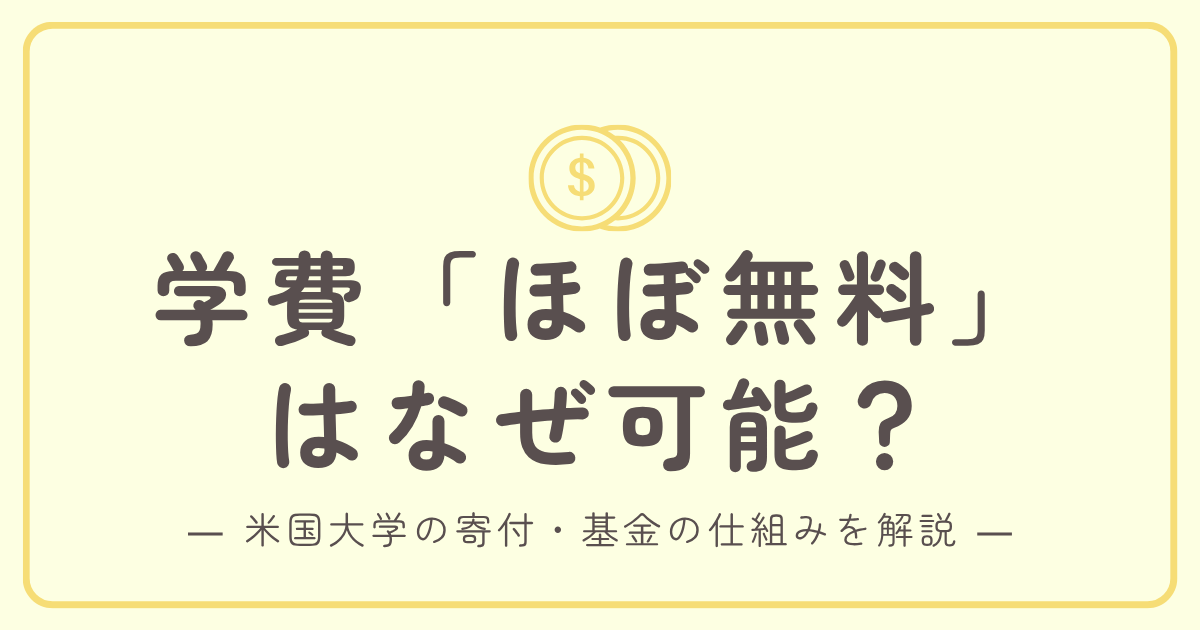

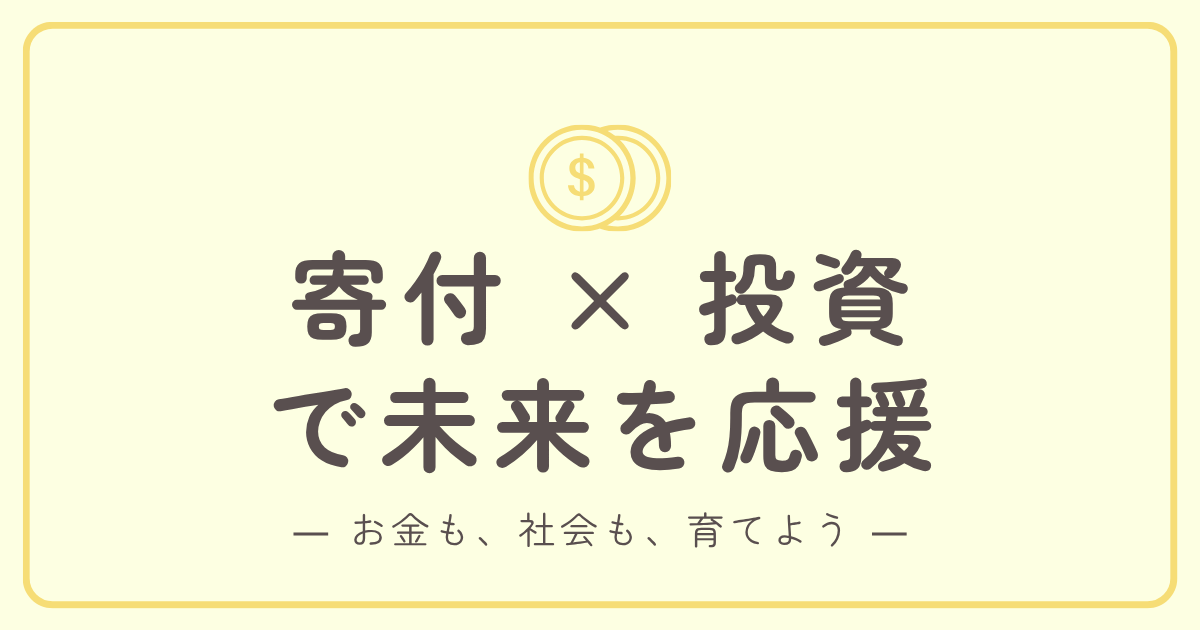

コメント