※本記事は、過去にFPからの目線として書いた内容です。
現在のCampus Labでは、助言や情報提供ではなく、学びや考察の記録を目的としています。
■ FPの役割は「正解を教えること」ではない
ファイナンシャルプランナー(FP)は、お金の知識を教えてくれる人、正解を提示してくれる人――そう思われがちです。ですが本来の役割は、すべてを教えることではなく、クライアントが自分で判断できるように導くことです。
人生では、住宅購入・教育費・老後・転職など、お金の選択が何度も訪れます。そのたびに誰かの答えを待っていたら、不安はいつまでも消えません。だからこそ大切なのは、自分で考え、選べる力を身につけることです。
■ FPは“伴走者”であり、“判断のコーチ”
判断力を育てるには、知識だけでは足りません。自分の価値観と照らし合わせ、選択の意味を理解し、納得して決める力が必要です。その過程では、試行錯誤や迷いも避けられません。
そこでFPの役割は、答えを押しつけることではなく、考えるプロセスを支えることだと考えます。
たとえば、保険を選ぶときに「これに入れば大丈夫です」と教えるよりも、
- なぜ必要なのか
- 入らなかったらどうなるか
- 他の選択肢との違いは何か
これらを一緒に考える方が、ずっと本人の力になります。
■ 従来型FPとコーチ型FPの違い
| 従来のイメージ | コーチ型FP |
|---|---|
| 答え・商品を教える人 | 一緒に考え、判断力を育てる人 |
| 「これが正解です」 | 「なぜそう考えるか」を問いかける |
| 依存を生む関係 | 自立を支える関係 |
■ クライアントにも必要な姿勢がある
FP任せにするのではなく、自分で考え・試してみる姿勢も大切です。完璧な答えを探すより、小さくても自分で選んでみる。その経験が、未来の判断力につながります。
失敗も含めて「自分で選んだ」経験は、誰かに教えられた正解より、ずっと強い財産になります。
■ まとめ:FPは“教える人”から“共に考える人”へ
- FPの理想は、知識を押しつける先生ではなく、判断力を育てるコーチ。
- クライアントの安心と自立の間に立ち、迷ったときに道を照らす存在。
- 答えを与えるのではなく、“自分の答え”を見つけられるように支えることこそFPの価値。
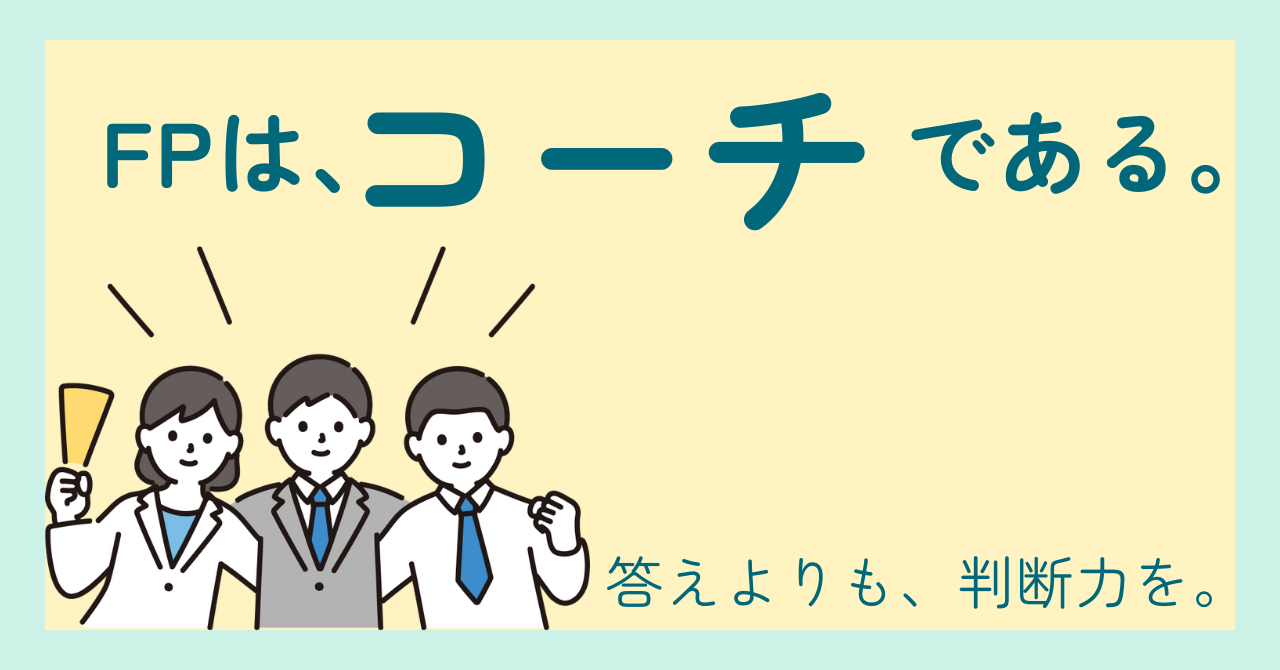

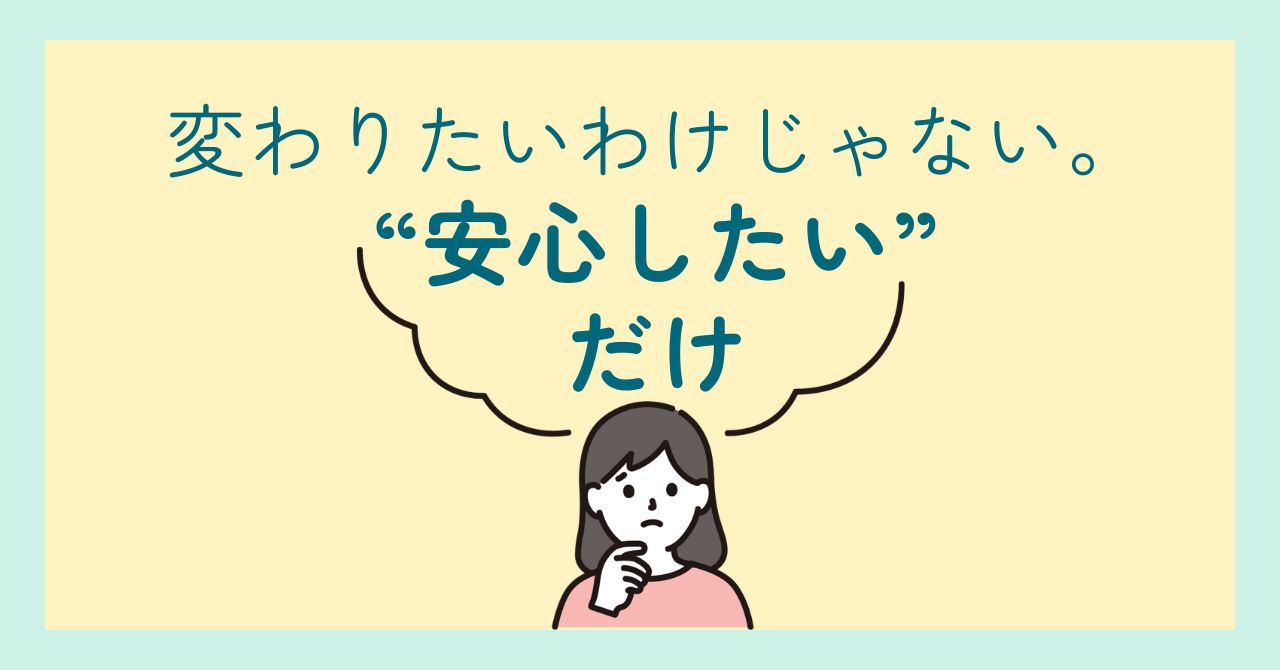
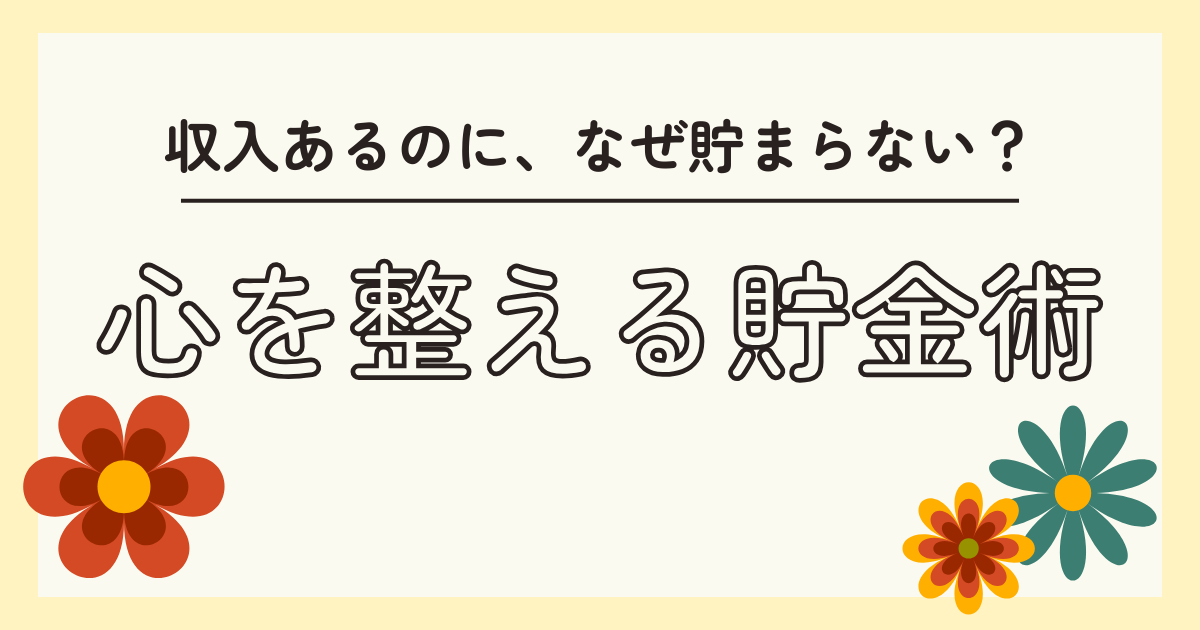
コメント