※本記事は、過去に書いた内容です。
現在のCampus Labでは、助言や情報提供ではなく、学びや考察の記録を目的としています。
日本では、震災やテレビ企画があると寄付が一気に集まります。東日本大震災や海外災害、24時間テレビなどはその典型で、「誰かを助けたい」という思いは確かに存在します。ただ、その行動は“きっかけ依存型”になりやすく、平時は寄付が日常的に行われているとは言い難いのが実情です。
なぜ、日米で寄付行動のスタイルが異なるのでしょうか。
日本:きっかけがあれば集まるが、日常化は弱い
日本では、寄付を行う際に大きなイベントや強い感情が必要になる傾向があります。
背景にはいくつかの理由があります。
- 使途の見えにくさ
自分の寄付がどこに使われ、どの程度役立っているのかを知る機会が少ない。 - 返礼文化の強さ
ふるさと納税が広がったのも、返礼品という明確なメリットがあったからこそ。無返礼の寄付はどうしても影が薄い。 - 共有文化の弱さ
「寄付した」と言うことが自慢のように受け取られるため、話題にしづらい。
つまり、関心はあるのに、続けるための仕組みが整っていないと言えます。
アメリカ:寄付が日常になる理由
一方でアメリカでは、寄付があくまで日常的な社会参加として受け止められています。
① 税制の浸透
寄付は税控除の対象として広く使われ、家計の一部に組み込まれています。所得控除だけでなく、税額控除もあり、「寄付することが合理的」と認識されている点が大きいです。
② コミュニティ文化
教会や地域団体、大学同窓会が寄付と密接に結びつき、寄付はコミュニティを維持する行動として位置づけられています。
③ 寄付の“可視化”がうまい
校舎の壁に寄付者名を刻むドナーウォール、成果を伝える年次レポート、寄付者向けイベントなど、寄付が社会的承認につながる仕組みがあります。
寄付は善行であると同時に、社会的なステータスでもあり、寄付すること自体が“誇らしい行動”とみなされているのです。
日本で寄付を日常化するには
では日本で寄付を根付かせるにはどうすればよいでしょうか。
① 小さく始める
月1,000円など、無理のない範囲で始めると心理的負担が少なく、継続しやすい。
② 使途を可視化
寄付先が成果をメールやレポートで共有するなど、寄付者が「関わっている実感」を持てる仕組みが重要。
③ 税制を“当たり前”に
寄付金控除には、所得控除や税額控除があります。
近年は電子版領収書を発行→e-Taxで申告でき、手続きのハードルが下がっています。
「寄付=確定申告」という一連の流れが習慣化すれば、寄付のハードルは一段下がります。
まずはやってみる
寄付は金額の大小ではなく、続けることが価値になります。
わずかでも誰かの役に立てるという実感は、投資と同じで「小さく始めて続ける」ことで大きな成果につながります。
寄付を“社会参加のひとつの形”として捉え、生活の中に少しずつ取り入れてみませんか。
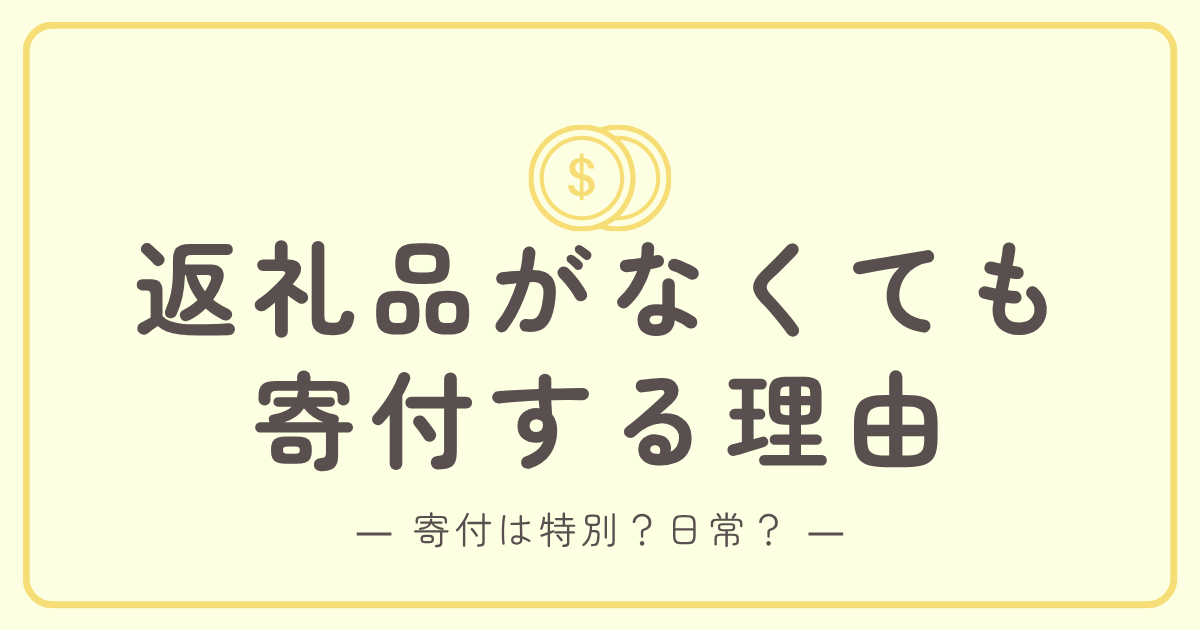

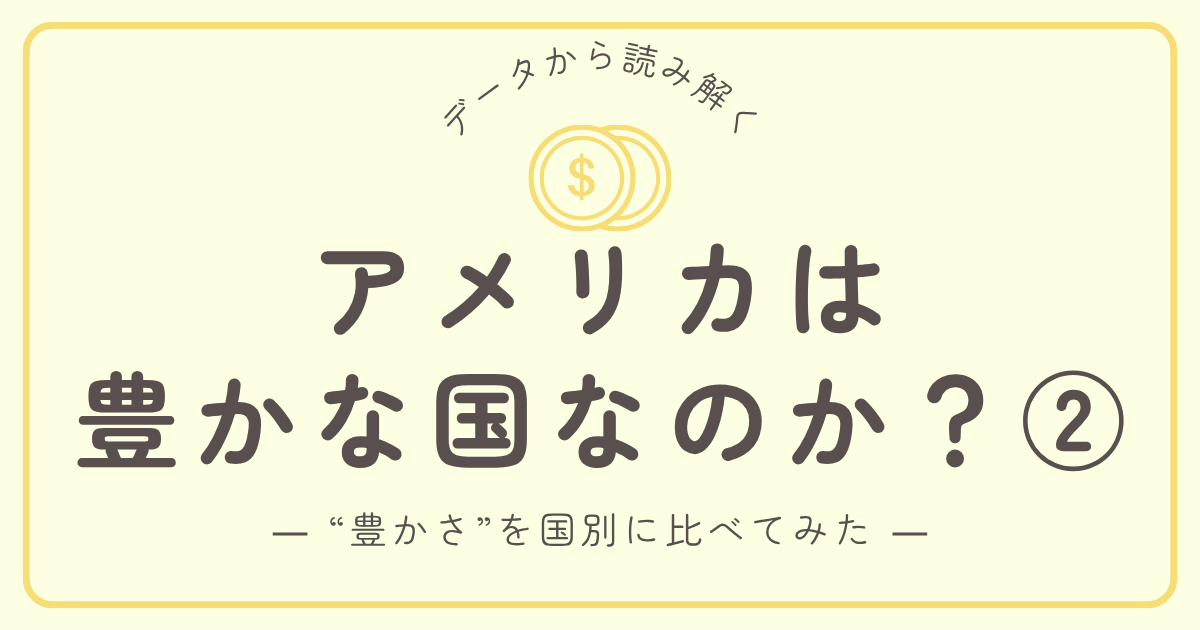
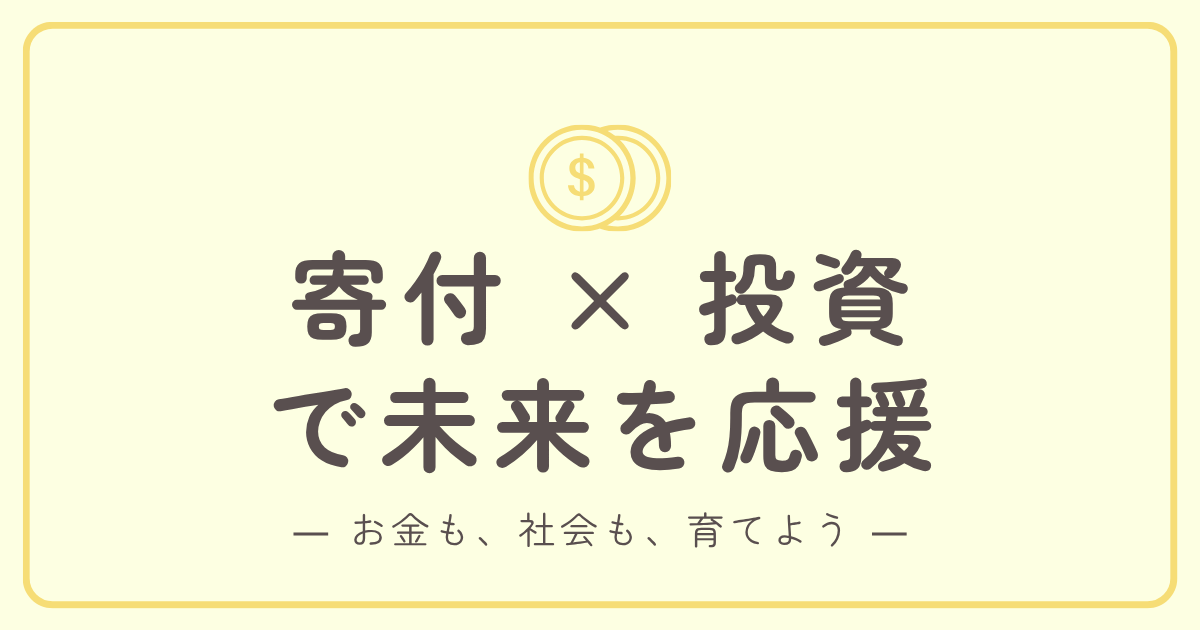
コメント