※本記事は、過去に書いた内容です。
現在のCampus Labでは、助言や情報提供ではなく、学びや考察の記録を目的としています。
シリーズ:手数料に惑わされない投資判断(補足/コラム編)
「安いのにすごい」「頑張ってくれてありがたい」――
私たちはいつの間にか、“がんばり”を前提とした安さを好むようになったのかもしれません。
けれども、その努力が続かなくなったとき、誰かが疲れてしまうこともあります。
今回は、「献身的=美徳」とされる背景を、少しやわらかく見つめてみます。
「安さ」と「努力」が結びつく社会
テレビでは「安くて美味しいお店」が称賛されます。
その裏で、店主が長時間働き、ギリギリの価格で頑張っている姿が“感動”として紹介される。
こうした物語は、「安さ=努力の証」「頑張る=美しい」という価値観を強化してきました。
「献身的=美徳」の文化的背景
日本では「他者のために尽くすこと」が長く美徳とされてきました。
戦後の復興期には「働くこと=善」とされ、 “自分のため” より “みんなのため” に頑張る姿が尊ばれた時代があります。
この文化は人の温かさを育てる一方で、
「自分を犠牲にしてでも支えることが正しい」という思い込みも生んでいます。
安さは一時的な善意、でも続けるには仕組みが要る
献身や工夫による「安さ」は短期的にはお客さま思いの善意です。
しかし長く続けば、働く人や品質が犠牲になることもあります。
“続けるための適正価格” を設定することは、むしろ責任ある選択だといえるでしょう。
「安さ=正義」から「持続する価値」へ
価格を下げることよりも、「良いものを長く続ける」こと。
それが社会全体にとっての“誠実さ”につながります。
手数料も同じです。
「払いたくない」 ではなく 「何に払っているのか」 を理解できれば、
支出は “損” ではなく “信頼への投資” になります。
※手数料を支払うことを推奨している訳ではありません。
まとめ
誰かが無理をして成り立つ「安さ」は、やがて誰かの負担になります。
本当の思いやりは、無理をせず続けられる仕組みを選ぶこと。
それが、社会も自分も支える選択につながるのだと思います。
「安くてすごい」も素晴らしいけれど、
「続けていける仕組み」こそが、これからの“美徳”なのかもしれません。
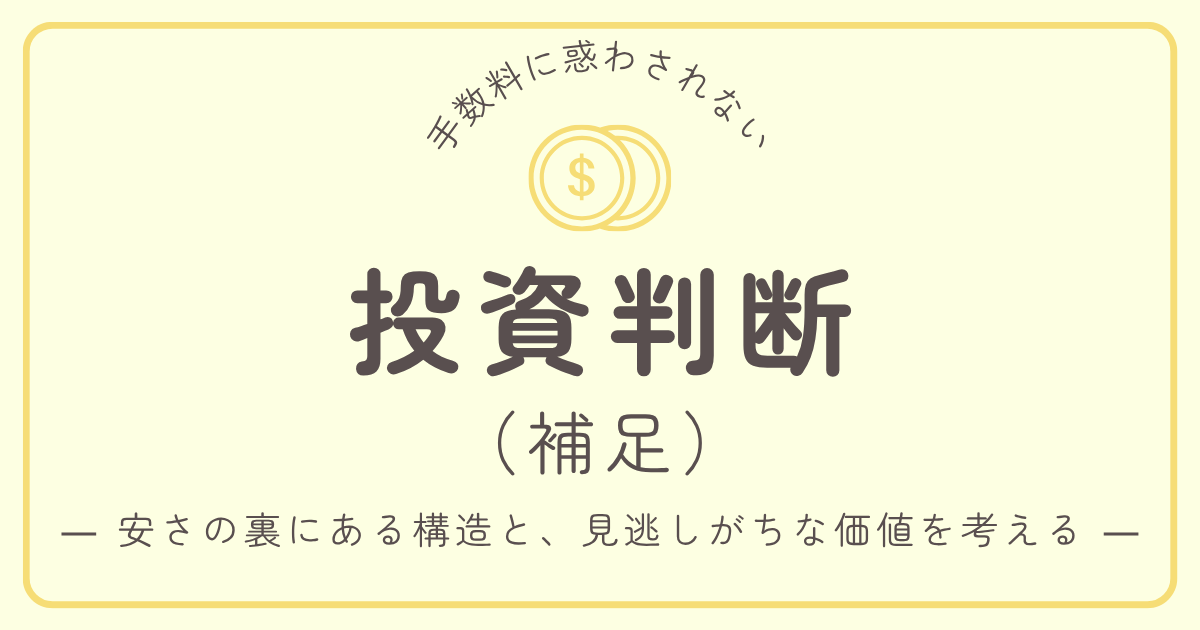

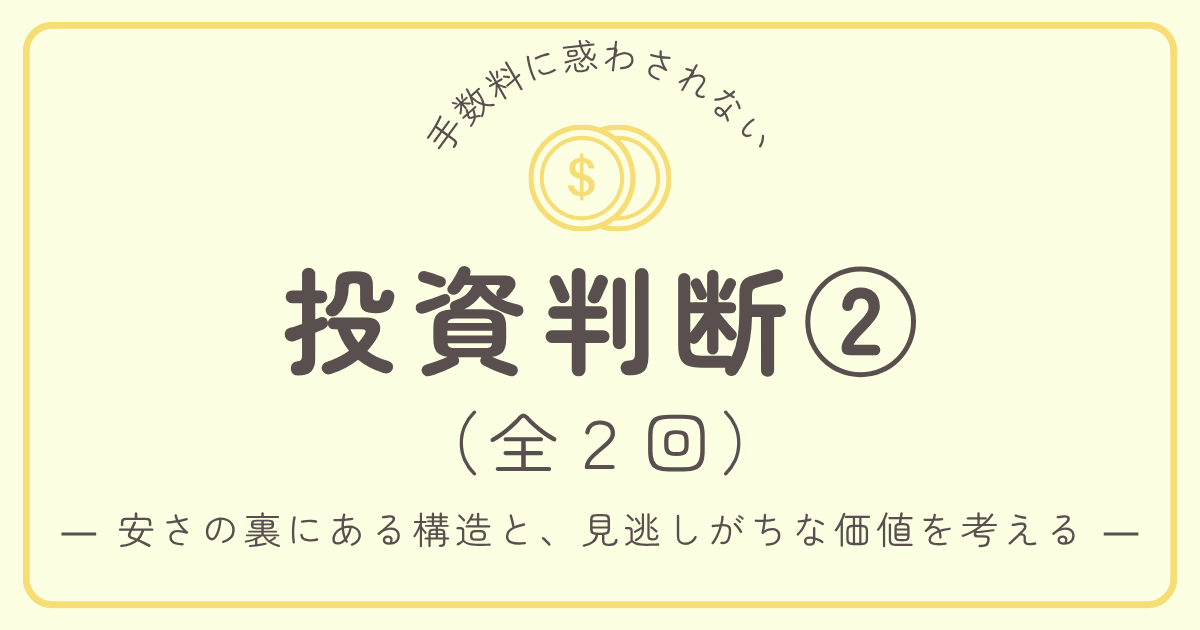
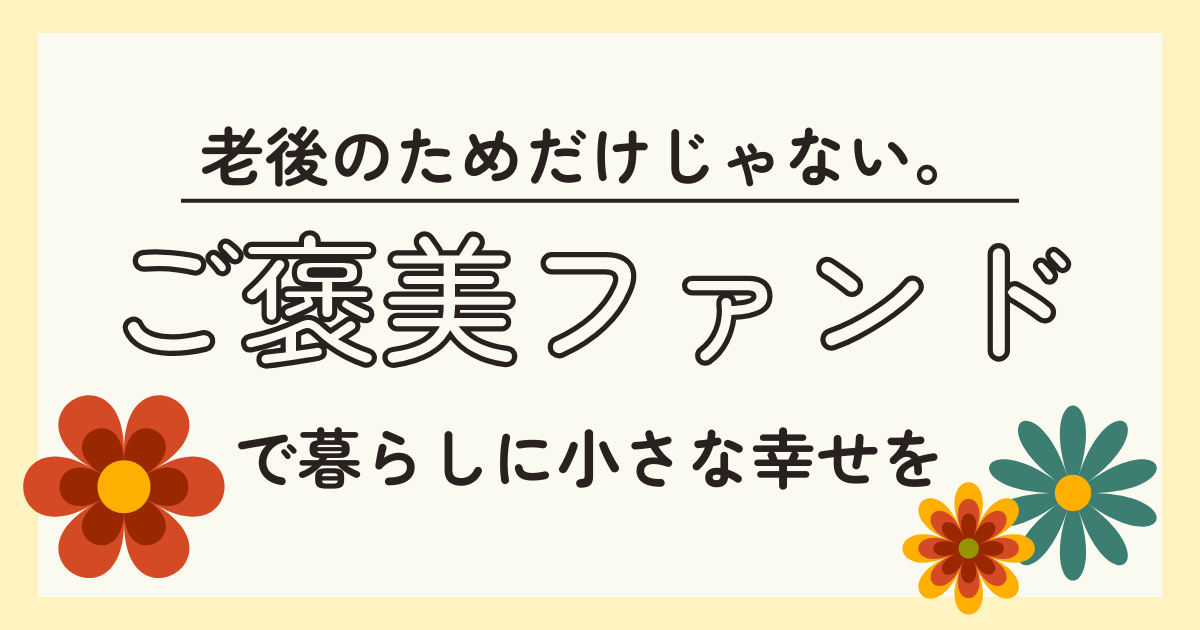
コメント