※本記事は、過去にFPからの目線として書いた内容です。
現在のCampus Labでは、助言や情報提供ではなく、学びや考察の記録を目的としています。
「FP相談をしてみたいけれど、何を聞けばいいのかわからない」「無料って本当に大丈夫?」――そんな不安を解消するために、FP相談の“仕組み”と“上手な活かし方”をわかりやすく整理しました。
FP相談の仕組みを理解しよう
FP相談には、収益の仕組みによっていくつかタイプがあります。ポイントだけサクッと。
①有料相談型(独立系FP・IFAなど)
・相談料を支払うタイプ。販売目的ではないため、中立的な提案になりやすい。
・向いている人:ライフプランをじっくり作りたい。
・注意点:料金とサポート範囲を事前に確認。
②無料相談型(販売連動)
・相談は無料。保険や金融商品の提案・契約で収益が出る仕組み。
・向いている人:まずは入口として話を聞きたい。
・注意点:自分の目的に合うかで提案をチェック。
③ハイブリッド型
・相談料+一部紹介料の併用。費用と中立性のバランスを取りやすい。
どれが良いかではなく、まずは収益の仕組みを知ることで安心して選べます。
相談を充実させる、2つの準備
これだけでOK。 ①現状把握 と ②目的の意識。
①現状把握(数字はざっくりでOK)
「収入がある=貯蓄できている」とは限りません。 次の5つだけメモしましょう。
・手取り(毎月・年)
・固定費(家賃・通信・保険料など)
・変動費の目安(食費・交際費など)
・貯蓄額/投資額/予備費
→ 数字があると、提案の現実性と比較のしやすさがグッと上がります。
②目的の意識(ざっくりでOK)
「何のために・いつまで・どのくらい」。 この3点だけ考えてみましょう。
・NISA/iDeCo: 何年後に、何に使う?(老後・住宅・教育・独立など)
・リスク許容度: 価格が上下しても心配になりすぎない範囲は?
・住宅ローン: 借りられる額より、無理なく返せる額を基準に
予定は変わってOK。 あとで見直せる前提で、まずは仮の目的を置いてみましょう。
提案の受け止め方(見るべきポイント)
・前提条件(収入・支出・目的・期間)が自分に合っている?
・メリットだけでなく費用・リスク・代替案の説明がある?
・提案が早くない?(ちゃんと話を聞いて提案してくれている?)
・比較やセカンドオピニオンで納得度を高める。
まとめ:仕組みを知れば、相談は味方になる
・タイプは3つ。まずは収益の仕組みを理解。
・相談前は現状把握と目的の意識だけ整える。
・良い提案=「自分に合っている」と言えるもの。
仕組みを知ることが、良いFP相談への第一歩。
「教えてもらう」から「一緒に考える」へ。
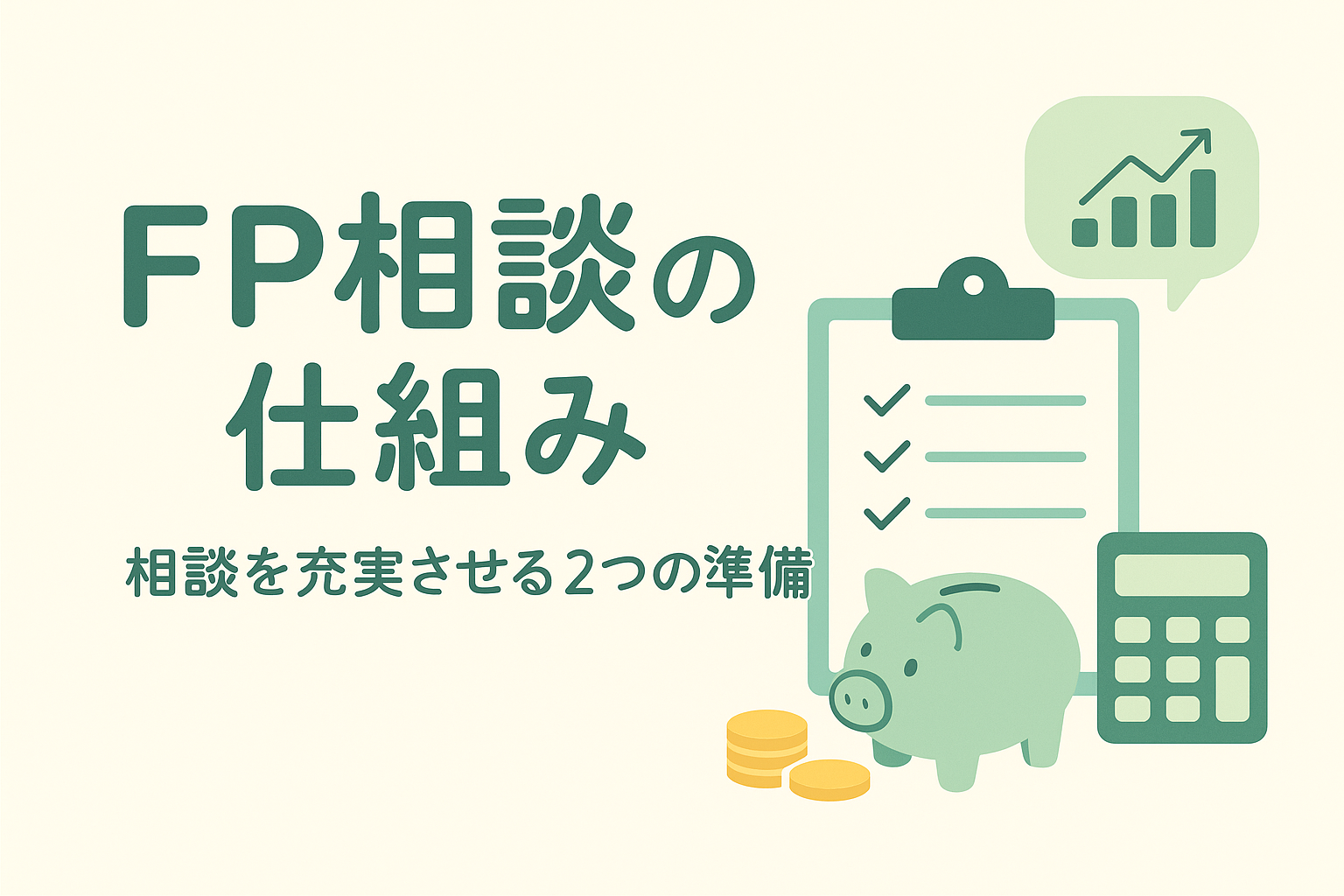
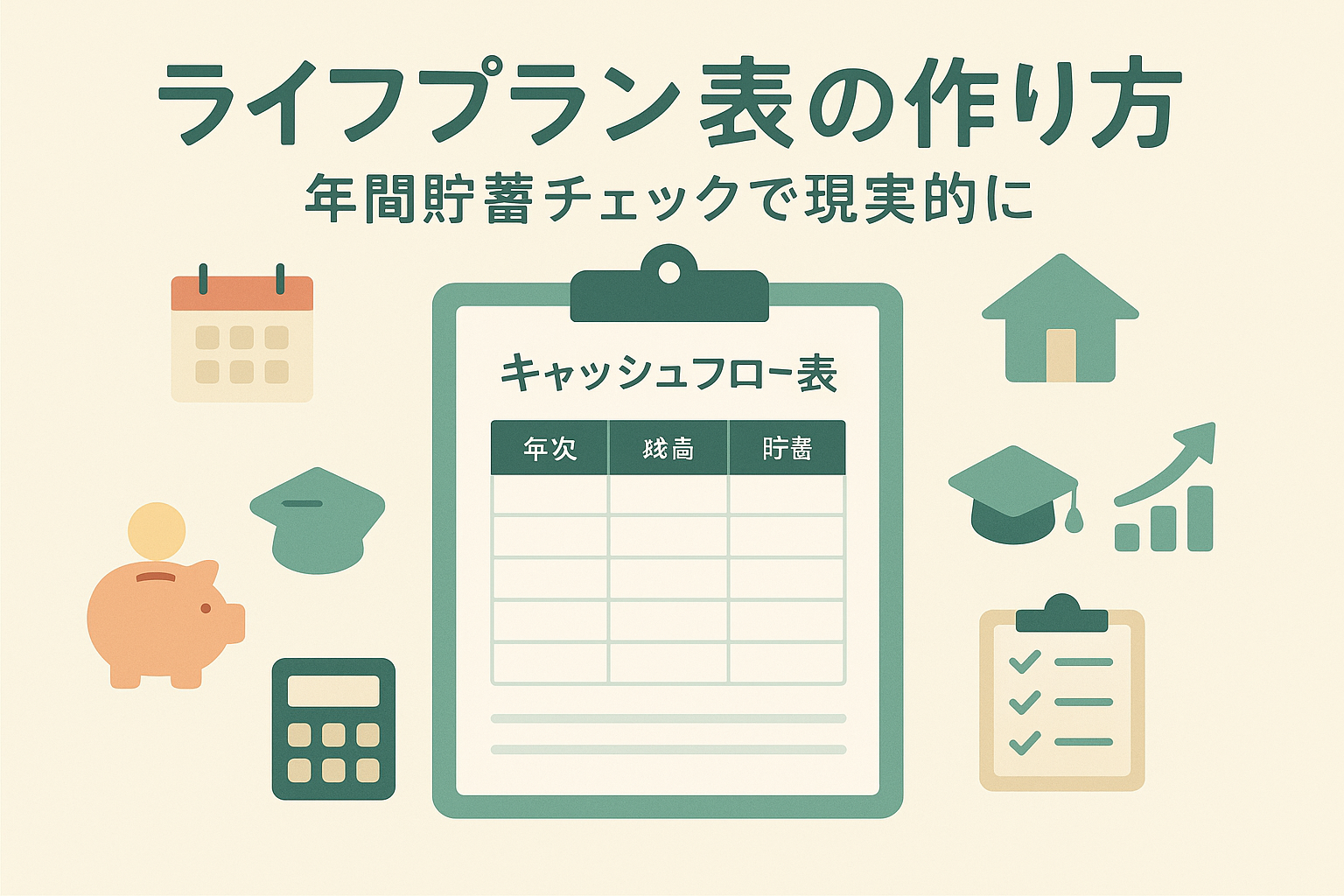
コメント